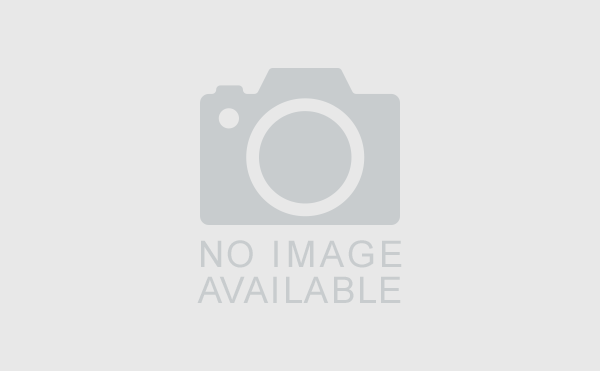キャッシュフロー表のすすめ
将来にわたり必要となる資金を見通しすためには、収入及び支出の予想とともに必要な資金額との対比などを行い、長期的な収支計画を立てることができるキャッシュフロー表の作成が必要です。 キャッシュフロー表の作成ステップは、①現在の財産状況の把握、②収入・支出項目の分類、③年間収支の概算、④②で決めた各項目の将来予測、となります。
①現在の財産状況の把握
財産の状況を可視化することは、生涯に及ぶ資金計画の出発点になります。 ここでいう財産とは「資産」と「負債」の両方を指します。現在の資産と負債を構成している項目とその金額を書出し、資産と負債のそれぞれの合計額を算出し、資産から負債を差し引いた正味財産を算出しておきます。正味財産がマイナスなら債務超過の状態にあることになります。
②収入・支出項目の分類
次に収入と支出の双方について、金額を集計する単位となる項目を決めます。毎年発生し普通は金額に大きな変化がない項目(経常項目)とそれ以外の項目(非経常項目)とに二分したのち、それぞれをさらに小さな項目に分類するとよいでしょう。ここで注意しなければならないことは、項目をあまり細かく分けないことです。なぜなら、キャッシュフロー表の目的は収入や支出項目を細かく分類して分析することではなく、それらの構成と金額規模を大づかみして、今後の推移を予測することだからです。
日本FP協会のサイトにキャッシュフロー表の書式例(ひな型と呼んでおきます)があります。ここでは、経常収入として「本人の収入」「配偶者の収入」の2項目、経常支出は「基本生活費」「住居生活費」など5項目、非経常収入は「一時的な収入」の1項目、非経常支出を「その他の支出」「一時的な支出」の2項目としておきます。 このひな型を参考に、家計の特徴に合わせて、収支の状況とその変化を可視化しやすくなるように項目を立ててみるとよいでしょう。
③年間収支の概算
直近の1年間の収支実績を元に収入と支出の総額を調べて、その内訳を②の分類にあてはめて行きます。家計簿を付けている場合はこれを利用できますし、付けていない場合でも預金通帳やクレジットの利用明細などで②の大まかな項目に仕分けできる程度の情報は得られるでしょう。
④各項目の将来予測
最後に各項目について、将来の予想を行い各年次の金額を記入していきます。③で計算した金額を出発点として、就職・退職や子の入学、結婚などの重要なライフイベントを境に階段状に金額を増減させていくのが基本シナリオになります。②で経常項目と非経常項目に分けておいたのは、毎年定額が発生すると想定できる項目と、不定期に発生する項目とで金額の想定方法を変えることが容易になるためです。
表の最終年をいつにするかは特に決まりはありませんが、老後の生活資金確保の手段の検討はキャッシュフロー表の重要な目的なので、自分(既婚の場合は配偶者も)が生涯を終える地点をゴールに設定するのがよいでしょう。 なお、物価の上昇をどう織り込むかが課題になりますが、いったんは上昇率(インフレ率)は考えず現在の価格をそのまま書き込んでおくとよいでしょう。
次回以後は、今回触れなかった貯蓄残高の記入法について述べ、収入及び支出項目のうち将来の推計に多少手間がかかりそうなものについて、算定の要領を記していきます。