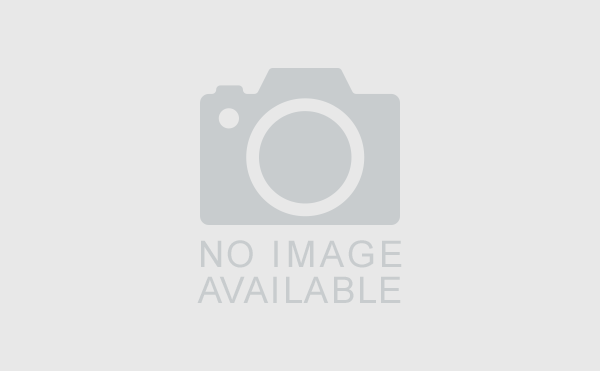キャッシュフロー表のすすめ 2
前回は、将来の資金計画を立てるうえで必要となるキャッシュフロー表の基本的なかたちを紹介しました。現在の財産状況を把握して、収入項目と支出項目のそれぞれの項目を決めて年間の収入額及び支出額を予測し、その結果としての各年末の財産の推移を算出するというのが基本の流れとなります。
前回は説明を省いていましたが、キャッシュフロー表書式例(ひな型)の最下段に「貯蓄残高」と記された項目があります。ここが各年末の財産の額を記入する箇所になります。預貯金に限らず株式、債券、投資信託などの金融商品の合計額をここに記入します。金融商品以外の不動産や貴金属、その他資産価値のある物品も価格を見積もって加えてよいでしょう。ただし、自宅不動産や自動車などは、将来売却して現金化する予定があるような場合以外は加算すべきではないでしょう。金融商品やその他の資産の種類別に項目を設けてもよいし、資産の中身は別の帳簿で管理することにしてここには合計額のみを記入することにしてもよいでしょう。
将来の支出項目の計算では、物価上昇率をどう反映させるかが問題になります。日本銀行の物価展望(2025年4月)によると、今後3ヵ年の生鮮食品を除く消費者物価上昇率は、2025年度2.2%、26年度1.7%、27年度1.9%と予測されています。ニッセイ基礎研究所の中期経済見通し(2024年11月)では、2024年度から34年までの10年間の消費者物価上昇率(生鮮食品を除く)を平均を1.7%と予想しています。これらの物価予想を根拠に例えば年率2%の上昇率を想定し、1年後の支出金額は現在の物価水準に1.02を掛けた金額、2年後は1.02の2乗(1.0404)を掛けた金額、以後3乗、4乗というように、上昇率1.02を累乗した数値を掛けて各年度の支出予想額を算定してキャッシュフロー表に記入します。
一方で保有している金融資産(ひな型では預貯金)の増加率(年利回り)を想定し、支出と同じように、想定した利回り(2%なら1.02)の累乗を掛けて各年度末の金融資産の金額を想定します。利回りを掛ける前の各年度の残高には、追加及び取崩しによる増減を加減します。注意していただきたいことが2つあります。まず、ここでは将来の総額の変化の趨勢をつかむのが目的ですから、金融商品の種類別に利回りを細かく分ける必要はなく、全体に対し単一の利回りを想定すれば十分ということです。もう1つは、想定する利回りを、保有している金融商品の実際の利回りではなく目標値と位置付け、いろいろな数値を入れて将来の変化のシミュレーションを行ってみることです。つまり、金融商品の保有あるいは投資を物価上昇(インフレ)に対する防衛策と位置づけ、支出をカバーできる利回りの水準を見極めるために使うということです。
次回も、キャッシュフロー表の作成にあたって想定が難しい項目や気を付けなければならない事項を書いていきます。